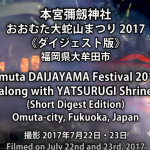こんにちは、ライターの幸森です。
先日、経営する店の前で“あるはずのないクリーニング屋”を探すおばあちゃんに出会いました。
一緒にクリーニング屋を探してみたけれど、やっぱり見つからなくて。
「どうしたらいいですか?」と助けを求めたのは、このまちで高齢者ケアに取り組んでいるプロ集団。
役所の窓口は閉まっている休日の出来事でしたが見事な連携プレーで対応して頂き、おばあちゃんは無事にご自宅へ送り届けて頂くことができました。
日本の高齢化の10年先をいくと言われる大牟田では、こんな風に誰もが安心して出歩けるまちを目指して毎年とある訓練が行われています。
『徘徊SOSネットワーク模擬訓練』の名称でスタートしたその訓練は今年新たに『大牟田市ほっとあんしんネットワーク模擬訓練』と名称を変更。
毎年9月の『世界アルツハイマーデー』に合わせて、市内全校区で実施されていますがご存知でしょうか?
今年は台風の影響で中止となった模擬訓練でしたが、そこに込められた想いや関わる人たちのことが雑誌『コトノネ』に掲載されました。
市外の方はもちろんですが、市内の皆さんにも是非読んで頂きたい記事だったのでご紹介します。
目次
コトノネ
今回ご紹介する『コトノネ』は、東日本大震災を契機に創刊された雑誌です。
被災地の障がい者や障がい者施設の復興支援として、全国の障がい者施設・就労支援施設の経営改革に関する様々な提案を行うべく2012年から発行されています。
雑誌「コトノネ」は、全国の障害者施設、就労支援施設の経営改革に関する様々な提案をおこなうことを目的に、2012年1月に創刊された雑誌です。東日本大震災を契機に、被災地の障害者および障害者施設の復興支援をしたいという想いから創刊を決意しました。
震災により、被災地の障害者や施設も大きな被害を受けました。震災からの「復旧」を越え、今後どんなに危機的な状況を迎えてもそれを跳ね返すだけの力を備えた復興、を目指して、障害者施設、就労支援施設が「復興」に向け新しい仕組みを創り上げる。本誌はその一助になりたいと考えています。
「コトノネ」の「コト」は「事」であり、「言」や「異」であります。それらが入り混じりあいながらくらしに様々な「音色」を表現していく。困難を乗り越え、新境地を切り拓いていくために、今まで「異」であった人々とも積極的に言葉を交わし、新たな「ハーモニー」を紡ぎだす。そんな思いが込められています。今後の「コトノネ」に、どうかご期待ください。
引用:コトノネ公式Webサイトより
特集「認知症なの。よろしくね」と言える町へ
今年11月20日に発行された『コトノネ』vol.32に、大牟田市の高齢者への取り組みが取り上げられました。

「障がい者に関する雑誌でなぜ高齢者?」と思われる方もいるかもしれませんね。
年に4回発行されているコトノネ、表紙を開くと最初にこんな言葉が綴られています。
手にとっていただいて、ありがとう。
コトノネは、障害者の「働く姿」を通して、
「生きるよろこび」を伝えたくて生まれました。
それは、誰にでもある「生きるよろこび」や
「生きづらさ」じゃないか、と気づかれることでしょう。
この本には、「障害者」という文字があふれています。
「障害」があるのは社会だから、
ほんとうは、「障害社」と書くべきなのですが。
また、障害者でなければ、健常者ですが
果たして「常に健やかなる人」はいるのか、とも、
大きな疑問を抱かれることでしょう。
この世には「障害者」も「健常者」もいない、
おなじ人がいるだけです。
誰もが「生きづらく」、
その中に「生きるよろこび」を求めて生きています。
そう信じて、コトノネをお届けします。
胸に深く刺さるのが『この世には「障害者」も「健常者」もいない、おなじ人がいるだけです。』との一文。
“あなたが抱える「生きづらさ」も、私が抱える「生きづらさ」も、形は違えど同じ「生きづらさ」であり、「生きるよろこび」を求める気持ちに何の差異があるのか”
と投げかけられているような気がします。
大牟田市が取り組む高齢者福祉は
“「高齢者」とか「認知症」とかじゃなく、おなじまちに暮らすおなじ人として、互いにどう支え合っていったら良いのか一緒に考えていきませんか?”
というスタンス。(だと私は解釈しています。)
だからこそきっと『コトノネ』の伝えたいことと重なる部分を見つけて頂いたのではないかなと。
“特集「認知症なの。よろしくね」と言える町へ”と題して、大牟田市が取り組む『ほっとあんしんネットワーク模擬訓練』のことや関係者インタビューが掲載されました。
立ち位置の異なる6人が語った正直な言葉たち

語ったのは立ち位置の異なる6人。
立ち位置が変われば当然関わり方も視点も異なり、語られる言葉も様々です。
インタビューを受けた6人それぞれが抱く課題意識や関わる中で感じたこと、知って欲しいことが等身大の言葉で綴られていて、いわゆる“綺麗事”がありません。
日本全国、そして海外からも視察が来るほど注目される大牟田市の取り組みですが、中で取り組めば取り組むほどその難しさや未完成さを感じている人たちがいます。
専門職として常に最前線で取り組んできた猿渡進平さんのインタビューにはこんな言葉がありました。
「認知症の人が外出したら、それを支えられる地域になってきたと思います。ただ、外出したい町ではない。」
また、認知症ケアのプロとして数々のメディアにも出演されている大谷るみ子さんのページは、こんな見出しが付けられています。
「訓練は本当は、自分たちのためなんだけどね」
認知症を発症した人たちの「生きづらさ」を身近で感じてきたお二人だからこその言葉は、考えさせられるものがあります。
そして実は今回、『まちの人(商店主)』の立ち位置で私も6人のうちの1人としてインタビューを受けました。
初めて認知症らしきおじいちゃんに声をかけた時の不安な気持ちとか、それから視点が少し変わったこととか、その出来事を発信したことで起きた身の回りの変化とか……
正直に語った“何気ないことだけど知って欲しいこと”をしっかり詰め込んで頂いています。
『コトノネ』で綴られているのは成功事例としての“綺麗事”じゃなくて、まだまだ走り続ける大牟田の“今”。
ありのままの姿だからこそ深くて温かい記事です。
誰もが当事者予備軍
今自分に“高齢者”や“認知症”は関係ないと思っているあなたも、いつ当事者や当事者家族、関係者になるかはわかりません。
認知症は高齢者だけの病気ではなくて突然あなたや家族に発症するかもしれないし、おなじまちに暮らす高齢者は大勢います。
そしてあなたも私もいずれ、高齢者になります。
誰もがいつかは関わる可能性が高く、当事者になり得ることだから、ほんのちょこっとだけアンテナを向けてもらえたらなと思うのです。
それはいつしか自分が抱く「生きづらさ」を解消してくれることに繋がっているはずだから。
ちょっとでも関心を抱いて下さった方は是非『コトノネ』の特集記事も読んでみてくださいね。
コトノネの購入方法
大牟田市で『コトノネ』を直接購入できる方法は2つ。
①軒先書店(読者編集委員)彌永恵理さん
お店を構えられているわけではないので、電話で注文してお一人ずつお引き渡しとなります。
連絡先:090-7580-9044
②Taramu books&cafe
カフェを併設した書店Taramu books&cafeで注文を受け付けています。
所在地:福岡県大牟田市久保田町1-3-15
電話番号:0944-85-8321
みなさんこんにちは、キラキライター幸森です。 撮影技術向上の為、先日紅葉を撮りに行ってきました。 カメラ難しい・・・でも...詳細は店舗へご確認ください。
その他、福岡県内では下記書店にて販売中です。
- MARUZEN博多店
- 紀伊國屋書店福岡本店
- ジュンク堂書店福岡店
福岡県外の取扱書店については、コトノネ公式サイトをご確認ください。
この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます
最新記事 by 幸森 彩香 (全て見る)
- 大牟田市のボランティア情報【令和2年7月豪雨災害】 - 7月 9, 2020
- 【九州豪雨】大牟田市で被災された方へのお役立ち情報まとめ - 7月 9, 2020
- 【九州豪雨】大牟田市への支援方法まとめ - 7月 9, 2020